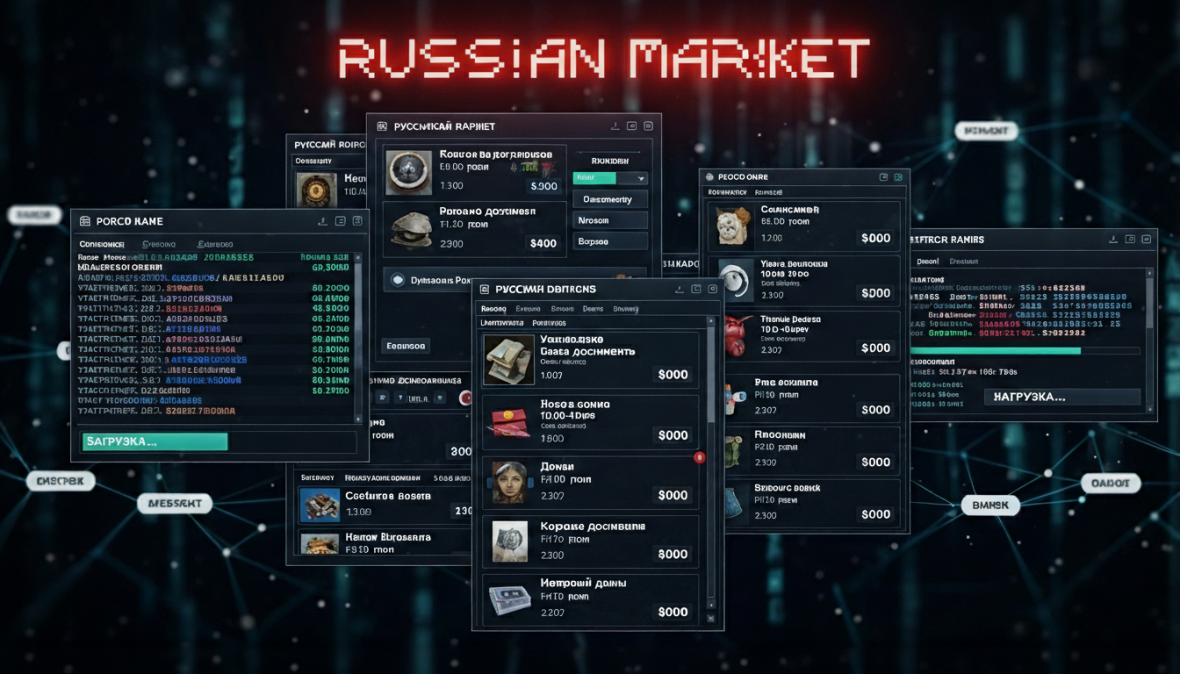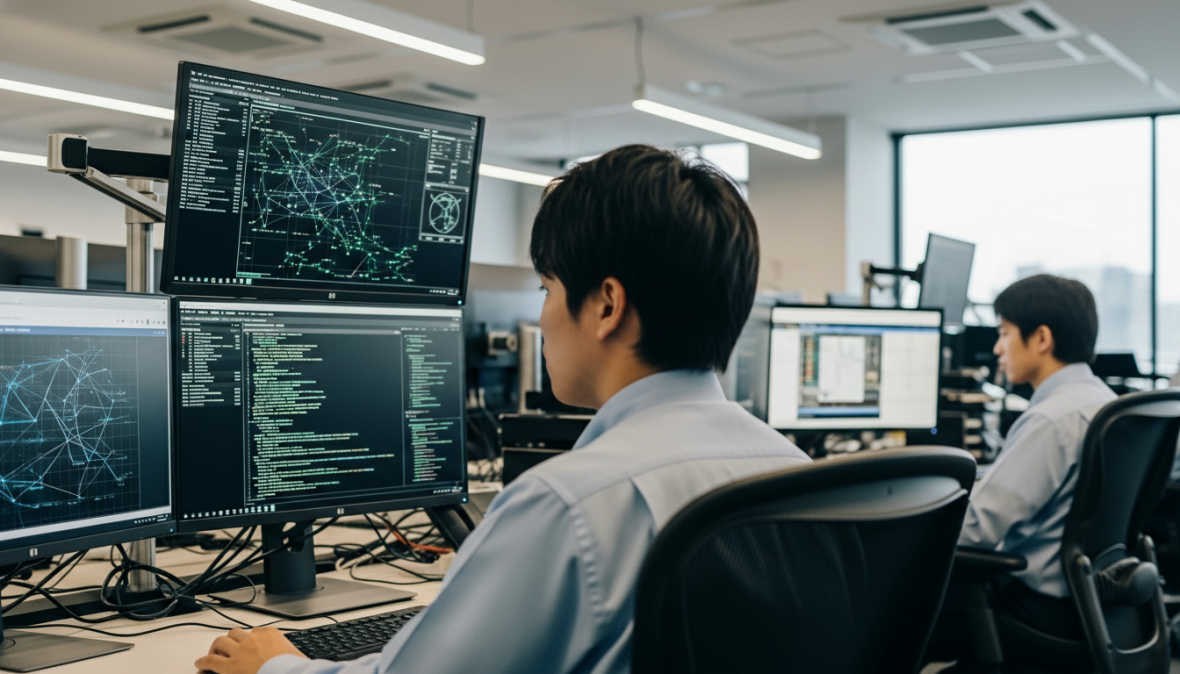サイバーセキュリティの現場にいると、最近とくに強く感じることがあります。
それは、「どの製品を導入するか」よりも前に、「その中身をどこまで信頼できるのか」が、以前よりもずっと重要になってきているということです。
少し前までは、有名なベンダーの製品を入れていれば安心、サポート契約を結んでいれば大丈夫、そう考えられていた場面も多かったと思います。
ただ、クラウドが前提になり、リモートワークが当たり前になり、社外サービスや外部パートナーとの連携が日常化した今、状況はかなり変わりました。
自分たちの管理下にない仕組みが増え、「何が、どこで、どう動いているのか」を完全に把握するのが難しくなっています。
現場で調査や診断をしていると、
「この仕組み、実は誰も詳しく知らないんです」
「前から使っているけど、細かい挙動までは見ていません」
そんな言葉を聞くことは、決して珍しくありません。
見えない仕組みの上に、重要な業務やデータ、そして企業の信用が積み重なっている。
その状態そのものが、気づかないうちにリスクになっていることもあります。
そうした環境の中で、ここ数年、静かに存在感を増しているのがオープンソースソフトウェアです。
派手な宣伝があるわけでもなく、「魔法のように安全になる」ものでもありません。
ただ、中身が見える、自分たちで確かめられる、という一点において、今の時代に合った選択肢だと感じる場面が増えてきました。
オープンソースという言葉には、「無料」「玄人向け」「扱いが難しそう」といったイメージが先に立つこともあります。
ですが、実際の現場では、
「だからこそ安心できる」
「だからこそ調整できる」
そう評価されるケースも確実に増えています。
この記事では、特定の製品を勧めたいわけでも、考え方を押しつけたいわけでもありません。
ただ、セキュリティの予防や診断に携わる立場から見て、
なぜオープンソースが今のセキュリティを支えているのか
なぜ日本では少し距離を置かれてきたのか
その背景を、現場で感じている温度感のまま整理してみたいと思います。
あわせて読みたい

TABLE OF CONTENTS
オープンソースとは何か──現場での受け止め方
オープンソースソフトウェア、いわゆる OSS は、ソースコードが公開されているソフトウェアです。
誰でも中身を見ることができ、必要であれば手を入れ、改変し、共有することもできます。
そのため、「無料で使えるソフト」というイメージを持たれることが多いのですが、現場で向き合っている立場からすると、価値はそこではありません。
本当に大きいのは、そのソフトが何をしているのかを、自分たちの目で確認できるという点です。
たとえば、
- このツールは、どの情報を集めているのか
- どんな条件で通信が発生するのか
- 想定外の挙動をする可能性はないか
そういったことを、仕様書や営業資料ではなく、実際のコードや挙動から確かめることができます。
セキュリティの仕事をしていると、「中で何をしているかは分からないけれど、とりあえず動いている」という状態が、どれほど不安定かを痛感する場面があります。
見えないものは、評価できません。
評価できないものは、守りきれない。
その意味で、「自分で確認できる」という性質は、オープンソースがセキュリティ分野で重視されてきた理由そのものだと感じています。
派手な機能や分かりやすいUIよりも、まずは中身が見えること。
それが、予防や診断の立場では、何よりの安心材料になることがあります。
インターネットとOSSの関係は、思っている以上に深い

企業のシステムだけでなく、実はインターネットそのものが、長いあいだオープンソースによって支えられてきました。
サーバーOSとして当たり前のように使われている Linux、
Webサーバーとして世界中で稼働している Apache や NGINX、
そして近年のクラウド基盤を形作っている Kubernetes。
名前を並べると、少し無機質に見えるかもしれませんが、これらは「実験的なツール」ではなく、日々、世界中の企業やサービスの裏側で使われ続けている、極めて実務的な技術です。
重要なのは、これらが「コストがかからないから」広まったわけではない、という点です。
もし不安定で、信頼できないものであれば、これほど長いあいだ、インターネットの基盤として使われ続けることはありません。
実際、止まってはいけない場所ほど、
失敗が許されないシステムほど、
結果的にオープンソースが選ばれてきました。
理由は単純で、中身を確認でき、問題が起きたときに原因を追え、必要であれば自分たちで直せるからです。
派手さはありませんが、「分からないまま任せる」よりも、「理解したうえで使える」ことが、長く使われる技術の条件なのだと思います。
オープンソースが世界の基盤になったのは、思想が評価されたからというより、現場で使い続けた結果、信頼が積み上がったから──そのほうが、実感に近い表現かもしれません。
セキュリティ分野でOSSが使われる理由
実務の中でOSSが選ばれてきた背景には、単なる思想や流行ではなく、現場で積み重なってきた明確な理由があります。
中身が見えるという強み
セキュリティ製品を選ぶ場面で、「機能が多いか」「UIが分かりやすいか」が話題になることは多いのですが、現場にいると、それよりも先に気になることがあります。
それは、この製品は、本当に想定どおりに動いているのかという一点です。
ブラックボックス型の製品では、
「このアラートは、何をきっかけに出ているのか」
「どのタイミングで、どこに通信しているのか」
「何を根拠に“異常”と判断しているのか」
そうした部分を、利用者側で細かく確認することは簡単ではありません。
仕様書やベンダーの説明を信じて使うしかない、という場面も少なくありません。
OSSの場合、必要であればコードを読み、実際の挙動を追い、「なぜそう動いたのか」を自分たちの手で確かめることができます。
監査やインシデント対応の現場では、この違いがそのまま判断の精度に影響します。
原因を推測するのか、根拠を持って説明できるのか。
この差は、後から振り返ると想像以上に大きいと感じることがあります。
現場に合わせて変えられる柔軟性
もうひとつ、OSSがセキュリティ分野で重視されてきた理由があります。
それは、「現場に合わせて変えられる」ことです。
攻撃は、業種や組織の規模、システム構成によって、姿を大きく変えます。
同じ攻撃手法でも、ある会社では致命的になり、別の会社ではほとんど影響が出ない、ということも珍しくありません。
OSSのセキュリティツールは、検知ルールやログの扱い方、アラートの条件などを、自分たちの運用に合わせて調整できます。
その結果、
「一般的には危険とされている挙動」ではなく、
「この会社にとって、本当に注意すべき挙動」
に焦点を当てた対策が可能になります。
現場で診断をしていると、“理屈としては正しいけれど、実務では使われないルール”が積み重なっている環境を目にすることがあります。
OSSは、そうしたズレを少しずつ修正しながら、自分たちの現実に近づけていける余地を残してくれます。
完成された答えを渡してくれるわけではありませんが、考えながら育てていけるという点で、セキュリティの実務とは相性が良いと感じています。
よく使われているOSSセキュリティツール
現場でよく目にするオープンソースのセキュリティツールを挙げると、次のようなものがあります。
どれも単体で完結するというより、役割を分担しながら組み合わせて使われることが多いツールです。
| ツール名 | 主な役割 |
|---|---|
| Wazuh | SIEM / EDR の中核となる基盤 |
| Suricata | ネットワーク侵入検知(IDS) |
| Zeek | 通信内容の詳細な解析 |
| Snort | パケットベースの IDS / IPS |
| OSSEC | ログ監視・ファイル改ざん検知 |
これらは「どれか一つを入れれば安心」という性質のものではありません。
たとえば、通信の異常を Suricata で検知し、その背景を Zeek で読み解き、端末やサーバー側の挙動を Wazuh で追いかける、といった使い方が現実的です。
視点の異なる情報を重ね合わせることで、「何かおかしい」という感覚を、「何が、どこで、どう起きているのか」という具体的な状況に落とし込めるようになります。
単体では点でしか見えなかったものが、組み合わせることで線になり、面になる。
OSSのツール群は、そうした立体的な可視化を前提に設計されているものが多いと感じています。
「OSSはウイルスが多い」という誤解について
現場で仕事をしていると、時折こんな声を耳にします。
「オープンソースって、なんとなく危ないイメージがあるんですよね」
その感覚自体は、決して不思議ではありません。
誰でも使える、誰でも触れる、という言葉だけを聞くと、「管理が甘そう」「攻撃者にも中身が見えてしまうのでは」と感じるのも自然だと思います。
ただ、実際の運用や調査の経験を重ねるほど、その印象は少しずつ逆転していきました。
オープンソースの世界では、
- 多くの開発者や研究者の目で、常にコードがレビューされている
- 脆弱性が見つかると、修正や議論が非常に速い
- 意図しない挙動や怪しい実装が、長期間放置されにくい
という環境が、ごく当たり前のように存在します。
「誰でも見られる」ということは、裏を返せば、「隠し続けることが難しい」ということでもあります。
セキュリティの観点では、この性質はむしろ強みになる場面が少なくありません。
少なくとも、「オープンソースだから危険」という単純な線引きができる世界ではない、というのが正直な実感です。
実際、世界中のクラウド基盤や重要なインフラの多くが、オープンソースの技術の上で動き続けています。
もし本質的に危険なものであれば、これほど長いあいだ、これほど広い範囲で使われ続けることはなかったはずです。
完璧だから使われているのではなく、問題が起きたときに、向き合える構造を持っているから使われている。
オープンソースに対する評価は、そのほうが実態に近いように感じています。
日本でOSS活用が進みにくい理由を、現場目線で見る
海外の事例と比べて語られることも多いテーマですが、日本の企業がOSSを積極的に採用してこなかった背景には、技術力の問題というより、意思決定や運用の文化が大きく影響しているように感じます。
慎重な意思決定文化
日本企業のシステム選定では、
- ベンダーサポートが明確に用意されていること
- 契約内容や責任範囲が文書で整理されていること
- 長期的に同じ構成を維持できる安心感
が、非常に重視される傾向があります。
この考え方自体は、決して悪いものではありません。
安定した運用を前提とする業務では、むしろ合理的です。
一方で、OSSは「まず動かし、試しながら調整し、必要に応じて育てていく」という性質を持っています。
この“試行”のプロセスが、事前にすべてを決めきる文化と噛み合わない場面があり、結果として選択肢から外れてしまうことも少なくありません。
ドキュメントと言語の壁
もう一つ、現場でよく感じるのが言語の問題です。
多くのOSSは、英語圏のコミュニティを中心に発展しており、最新の情報や細かな議論は、どうしても英語で行われます。
技術的な内容そのものよりも、「英語で情報を追い続ける必要がある」という点が、導入や運用の心理的ハードルになるケースは少なくありません。
日本語の公式ドキュメントや事例が十分に揃っていないことも、判断を慎重にする要因のひとつだと感じています。
既存システムとの関係
もう一つ見逃せないのが、既存システムとの関係です。
日本では、長年使われてきた独自システムやレガシー環境が、今も重要な業務を支えているケースが多くあります。
そうした環境では、OSSを取り入れることが単なるツールの置き換えでは済まず、
- システム構成の見直し
- 運用フローの変更
- 担当者のスキル習得
といった、複数の課題が同時に発生します。
結果として、「理屈では分かっているが、今は難しい」という判断に落ち着く。
この流れは、現場では決して珍しくありません。
それでも、少しずつ変わり始めている

一方で、すべてが停滞しているわけではありません。
スタートアップやクラウドネイティブな環境では、OSSはすでに「選択肢のひとつ」ではなく、自然な前提として扱われることが増えてきました。
最初からクラウドを前提に設計されたシステムでは、Linux やコンテナ、各種オープンソースのミドルウェアを使うこと自体が特別ではありません。
「OSSを使うかどうか」を議論する前に、「どう組み合わせるか」「どう運用するか」が話題になる──
そんな場面も珍しくなくなってきました。
また、行政や公共分野でも、少しずつ変化が見え始めています。
大々的な方針転換というよりは、特定の業務やシステムの一部にOSSを取り入れてみる、うまくいったところから次に広げていく、そうした現場主導の小さな採用が積み重なっている印象です。
一気に切り替えるのではなく、リスクを見極めながら、使えるところから使っていく。
その姿勢は、日本の組織文化とも相性が良く、結果としてOSSが無理なく根づいていく土壌になりつつあるように感じています。
見えない部分を、見える状態にしておくという選択
セキュリティの仕事をしていると、「何も起きていない状態」がどれほど貴重かを、あとから思い知らされることがあります。
問題が起きてから原因を探すよりも、平常時に仕組みを理解しているほうが、判断は圧倒的に楽になります。
何が通常で、何が異常なのか。
どこまでが想定内で、どこからが想定外なのか。
その線を、落ち着いた状態で引けているかどうかは、いざというときの対応を大きく左右します。
オープンソースは、決して万能な答えではありません。
導入すればすべてが解決する、というものでもありません。
ただ、
「自分たちで理解できる」
「自分たちで制御できる」
という選択肢を、確かに与えてくれます。
それは、製品やベンダーを疑うという話ではなく、自分たちの環境を、自分たちの言葉で説明できる状態に近づく、ということだと思っています。
今すぐ、大きく何かを変える必要はありません。
構成を入れ替えたり、新しい仕組みを導入したりしなくても構いません。
ただ一度だけ、自社の中で使われている仕組みを思い浮かべながら、「この中で、本当に中身を把握できているものはどれだろうか」と静かに問い直してみる。
その視点を持つこと自体が、すでに予防の一歩になっている──
現場にいる立場からは、そう感じています。

投稿者プロフィール

- イシャン ニム
-
Offensive Security Engineer
15年以上の実績を持つ国際的なホワイトハッカーで、日本を拠点に活動しています。「レッドチーム」分野に精通し、脆弱性診断や模擬攻撃の設計を多数手がけてきました。現在はCyberCrewの主要メンバーとして、サイバー攻撃の対応やセキュリティ教育を通じ、企業の安全なIT環境構築を支援しています。
主な保有資格:
● Certified Red Team Specialist(CyberWarFare Labs / EC-Council)
● CEH Master(EC-Council)
● OffSec Penetration Tester(Offensive Security)
最新の投稿
 Soc2026.02.10オープンソースは、いまのセキュリティをどう支えているのか
Soc2026.02.10オープンソースは、いまのセキュリティをどう支えているのか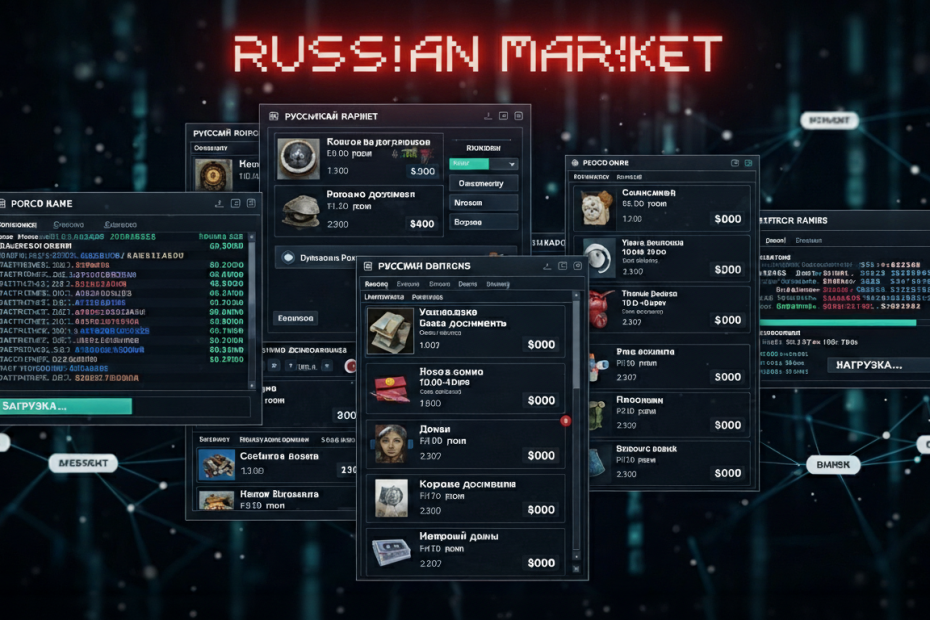 Black Hat2026.02.09Dark Web Market「Russian Market」が示す、いまの漏えいの形
Black Hat2026.02.09Dark Web Market「Russian Market」が示す、いまの漏えいの形 サイバーセキュリティの必需品2026.02.08パスワード管理が崩れたとき、最初に壊れるもの
サイバーセキュリティの必需品2026.02.08パスワード管理が崩れたとき、最初に壊れるもの LLM/生成AI2026.02.07AIセキュリティという新しい前提──信頼・リスク・耐性をどう築くか
LLM/生成AI2026.02.07AIセキュリティという新しい前提──信頼・リスク・耐性をどう築くか