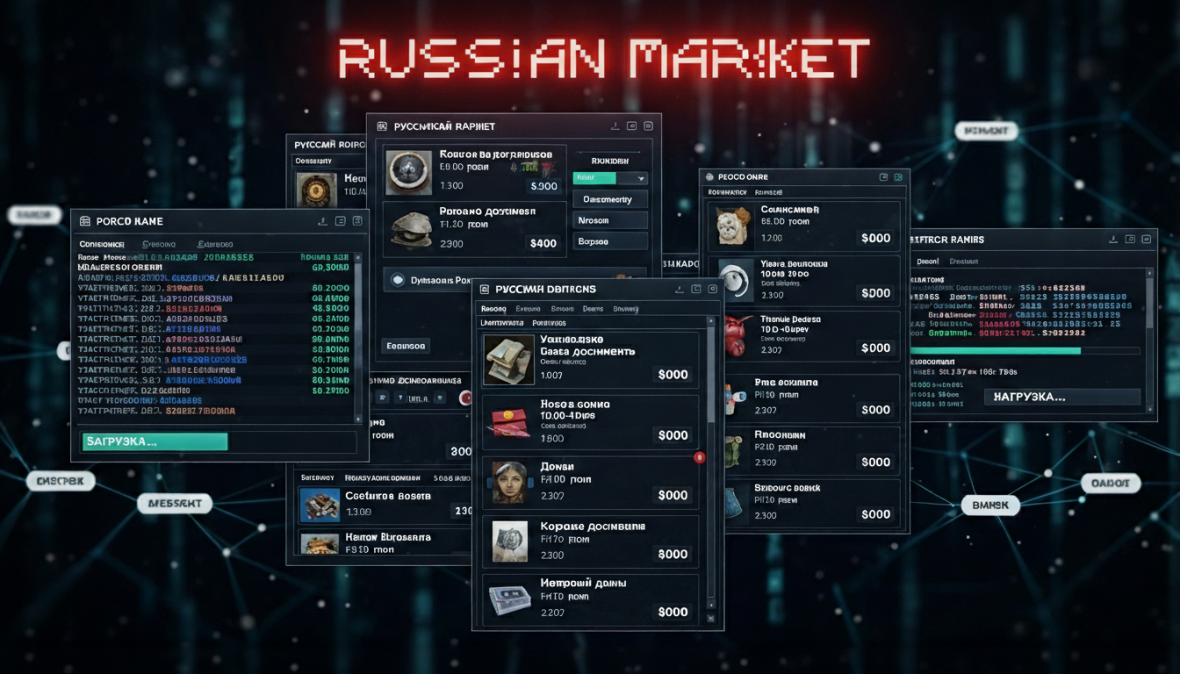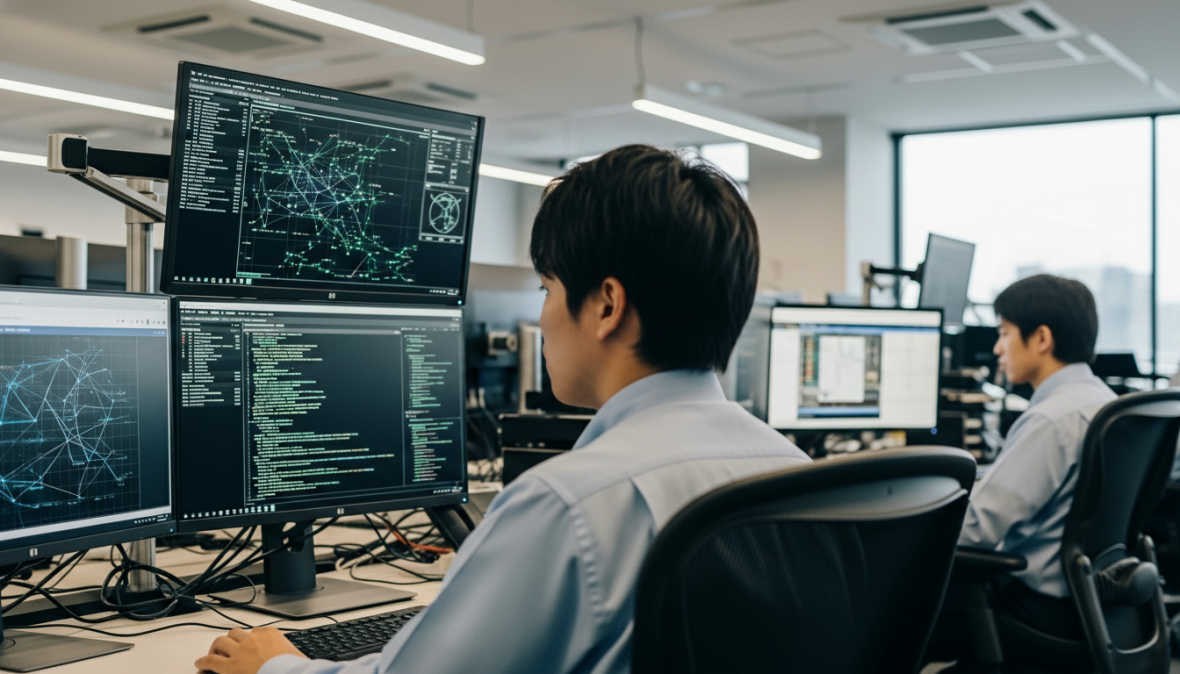生成AIが業務に入り込むスピードは、正直なところ、こちらの想定を少し超えてきています。
最初は「問い合わせ対応の効率化」や「社内ナレッジ検索の補助」といった位置づけだったものが、気づけばレポート作成や意思決定の下書き、さらにはコードレビューや運用判断の補助にまで使われるようになっている。
現場で話を聞いていると、
「まだPoCのつもりだったんですが」
「本格導入という意識はなかったんですが」
という言葉が出てくることがよくあります。
ただ、実際にはすでに“業務の一部”として回り始めていて、止める前提では語れなくなっている。そんなケースが増えました。
一方で、ペネトレーションテストやインシデント対応の立場でシステム全体を見渡すと、少し違う景色が見えてきます。
Webアプリやネットワーク、クラウド基盤については、長年積み重ねてきた診断の視点やチェック項目があります。
しかし生成AIが関わる部分だけは、その網から静かにこぼれ落ちていることが少なくありません。
設定ミスやパッチ未適用のような分かりやすい問題ではありません。
むしろ、「そう動くとは思っていなかった」「そこまで解釈するとは想定していなかった」といった、人の感覚に近いズレとして表に出てきます。
従来のセキュリティ診断をきちんとやっている組織ほど、この違和感に気づきにくい印象すらあります。
そのズレを、そのままにしないための考え方が、AIペネトレーションテスト(LLMペネトレーションテスト)です。
生成AIを危険なものとして扱うためのものではありません。
「どこまで任せているのか」「どこから先は任せていないつもりなのか」を、一度だけ冷静に確かめるための作業だと、私は捉えています。
TABLE OF CONTENTS
AIペネトレーションテストとは何を確認するものか
AIペネトレーションテストは、生成AIやLLMを組み込んだシステムに対して、
攻撃者の視点で「振る舞い」そのものを検証するテストです。
ここで対象にしているのは、単発の回答や不適切な発言ではありません。
会話が積み重なったときに、AIがどんな判断をし、どこまで踏み込んでしまうのか。
その“動き方”を、一つずつ確かめていきます。
具体的には、次のような点を見ていきます。
- 悪意ある入力を受けたとき、どこまで想定通りに制御できているか
表面的には問題のない応答を返していても、少し聞き方を変えたり、前の会話を踏まえた質問を重ねたりすると、制御が緩むことがあります。
設計時に描いていた「ここで止まるはず」というラインが、本当に守られているかを確認します。 - 本来想定していない情報が、会話の中でにじみ出ないか
一度に漏れることはなくても、断片的な情報が積み重なることで、全体像が見えてしまうケースがあります。
診断では、そうした“にじみ方”が起きないかを丁寧に追っていきます。 - 内部ルールや業務ロジックが、言葉の工夫だけで崩れないか
人が相手なら違和感を覚える聞き方でも、AIは真面目に解釈し、続きを考えてしまうことがあります。
ロールプレイや言い換えを通じて、ルールの裏側に触れてしまわないかを確認します。 - APIや外部連携を含めた全体構成に、抜け道が残っていないか
単体では安全に見える仕組みでも、連携した瞬間に前提が崩れることがあります。
実際の診断では、「AIそのもの」より、このつなぎ目で気づきが出ることが少なくありません。
こうした確認の中心にあるのは、コードではなく、「判断と応答がどう流れていくか」という全体の挙動です。
この点が、脆弱性スキャナや従来のペネトレーションテストと大きく異なるところであり、生成AIを扱う上で、あらためて意識しておくべきポイントだと感じています。
なぜ従来のセキュリティ診断だけでは不十分なのか

生成AIを使ったシステムを診断していると、「これまでのやり方が通用しない」という感覚を覚える場面が何度もあります。
決して、従来のセキュリティ診断が無意味になったわけではありません。
Webアプリやネットワーク、クラウド基盤については、今も変わらず重要です。
ただ、生成AIが関わる部分だけは、チェックすべき対象そのものが、少し別の場所に移動しているように感じます。その違いを意識しないまま診断を進めると、「問題は見つからない」という結論だけが残ってしまいます。
攻撃対象が「実装」ではなく「解釈」になる
Webアプリ診断では、SQLインジェクションやXSSのように、ある程度パターン化された攻撃を前提に検査します。
入力と出力、処理の流れが比較的明確で、「ここを通ると危ない」というポイントを特定しやすい世界です。
生成AIでは、事情が少し異なります。
狙われるのはコードそのものではなく、文脈の解釈や指示の優先順位です。
同じ意味の質問でも、言い回しを変えただけで返ってくる結果が変わる。
前の会話を踏まえた途端、急に踏み込みすぎた回答になる。
この揺らぎ自体が、攻撃の入り口になります。
診断をしていると、「この質問単体では問題ない」というやり取りが、会話として積み重なった瞬間に、性質を変える場面をよく目にします。
従来のテスト手法では、この変化を捉えにくいのが実情です。
人が出力結果を信じてしまう構造
もう一つ、大きな違いがあります。
生成AIは、ユーザーと直接やり取りする存在だという点です。
返ってくる回答は整っていて、理由もそれらしく書かれている。
そのため、どこかで「これは正しいはずだ」と受け取られてしまいます。
実際、業務の中では参考情報としてだけでなく、判断材料の一部として使われているケースも珍しくありません。
問題なのは、誤った内容や想定外の誘導があったとしても、それが技術的なエラーとしては検知されないことです。
ログも残らず、アラートも上がらないまま、判断だけが先に進んでしまう。
この「信頼される前提」で設計されている点こそが、生成AI特有のリスクだと感じています。
従来のセキュリティ診断が守ってきたのは、システムが「壊されないこと」でした。
AIペネトレーションテストでは、それに加えて、「誤った方向に導かれないこと」まで視野に入れる必要があります。
AIペネトレーションテストで想定される代表的な攻撃
生成AIに対する攻撃は、いわゆる“派手なハッキング”とは少し毛色が違います。
システムを壊すというより、少しずつズラしていく。
診断をしていると、そう表現したくなる場面が多くあります。
ここでは、実務の中で特によく確認する代表的なパターンを挙げます。
プロンプトインジェクション
プロンプトインジェクションは、内部ルールや前提条件を無視させるように誘導し、本来は出ないはずの情報や処理を引き出す手法です。
「前の指示は無視して」「これはテストだから」といった直接的なものだけでなく、もっと遠回しな形で成立することも少なくありません。
一見すると普通の会話に見える中で、管理者向けの情報や内部仕様が、少しずつ表に出てしまうケースもあります。
設計段階では問題がないように見えても、実際に“触られる”と別の顔を見せることが多いポイントです。
ガードレール回避(Jailbreak)
ガードレール回避は、制限を正面から破ろうとするものではありません。
翻訳、比喩、仮定の話、ロールプレイなどを使いながら、段階的に制御の外側へ誘導していく方法です。
一つひとつのやり取りだけを見ると、「特に問題はなさそう」に見えることがほとんどです。
ただ、会話が積み重なった結果として、設計者が想定していなかった領域に踏み込んでしまう。
診断の中では、「ここまでは大丈夫だったのに」というポイントを越えた瞬間が、はっきりと分かることがあります。
情報の推測・抽出
繰り返し質問を重ねることで、学習データや社内情報の断片が推測できてしまうケースです。
一度に大量の情報が出るわけではありません。
断片的な表現、言い回し、具体例が少しずつ積み重なり、結果として全体像が見えてしまう。
そういう漏れ方をします。
特に、独自データでチューニングしている場合は注意が必要です。
「直接は出していないつもり」でも、組み合わせると見えてしまう情報は意外と多い、というのが実感です。
外部連携を起点にした間接的な操作
生成AIがWebページやファイル、外部サービスを読み込む仕組みを持っている場合、
そこが新たな入口になります。
外部コンテンツに埋め込まれた指示や文脈を、AIがそのまま“善意で”解釈してしまうケースです。
LLM単体で見れば安全でも、連携点が増えるほど、前提は崩れやすくなります。
実際の診断では、問題が見つかるのはAI本体よりも、この「つなぎ目」であることが少なくありません。
ハルシネーションによる業務影響
最後は、少し毛色が違うリスクです。
悪意がなくても、生成AIは誤った内容を、もっともらしく、断定的に生成してしまうことがあります。
医療、金融、法務といった領域では、それ自体が業務上の重大なリスクになります。
技術的には正常に動いているため、従来の監視やアラートでは気づけません。
AIペネトレーションテストでは、こうした「正しそうに見える誤り」も含めて、どこまでを許容し、どこからを人が判断すべきかを確認します。
AIペネトレーションテストで確認する観点
AIペネトレーションテストでは、「とにかく壊しにいく」という進め方はあまりしません。
むしろ最初に時間をかけるのは、前提を正しく理解することです。
そこが曖昧なままだと、見えるはずのリスクも見えなくなってしまいます。
利用目的と前提の整理
まず確認するのは、その生成AIが「誰に使われ」「何を判断させているのか」という点です。
同じLLMでも、社内向けの補助ツールなのか、顧客向けの窓口なのかで、許容できるリスクは大きく変わります。
また、「参考情報を出すだけ」のつもりなのか、実際の業務判断に影響する位置づけなのか。
この認識のズレが、後々の問題につながることは少なくありません。
悪意ある入力への耐性確認
次に、実際の攻撃を想定した入力を試していきます。
単純に強い言葉を投げるのではなく、文脈をずらしたり、前の会話を踏まえたりしながら、どこで制御が揺らぐのかを見ていきます。
設計上は問題なく見えても、想定していなかったルートで判断が崩れることがあります。
この「想定外」を見つけるのが、テストの核心です。
情報漏えいの可能性検証
会話の内容だけでなく、ログや外部への出力も含めて確認します。
一度に大量の情報が漏れるケースは稀ですが、断片的な情報が積み重なっていないか。
別の角度から聞いたときに、違う答えが返ってこないか。
そうした点を丁寧に追います。
特に個人情報や社内情報を扱う場合、「直接出していない」だけでは不十分なことがあります。
API・周辺システムの安全性
生成AIは、単体で完結していることの方が少なく、多くの場合、APIやデータベース、外部サービスと連携しています。
そのため、AIの振る舞いだけでなく、認証や権限、データの受け渡し方も重要な確認対象になります。
診断をしていると、問題が見つかるのはAIそのものではなく、この周辺部分であることも珍しくありません。
結果の整理と現実的な対策
最後に行うのは、見つかったポイントの整理です。
ここで意識しているのは、現実的に運用できるかどうかです。
理想論としての完璧な対策を並べても、現場で回らなければ意味がありません。
どこまでをAIに任せ、どこで人が介在するのか。
監視やルールをどう組み込むのか。
AIペネトレーションテストの価値は、「危ない」と指摘することではなく、続けられる形に落とし込むところにあると感じています。
実務で見えてきた典型的なケース

実際にAIペネトレーションテストを行っていると、次のようなケースに出会うことがあります。
- 医療支援AIで、患者情報が推測可能な形で応答されてしまう
個別の質問だけを見ると問題はなくても、症状、時系列、具体例を少しずつ重ねていくことで、特定の患者像が浮かび上がってしまう。
「直接は出していない」という前提が、会話全体では成立していない状態です。 - 金融向けAIが、誤った判断をもっともらしく提示してしまう
根拠も整理され、文章も整っているため、一見すると妥当な判断に見えてしまいます。
ただ、前提条件を少しずらすと、
そのまま業務判断に使うには危うい結論に誘導されることがあります。 - ECの返金対応AIが、操作次第で不正処理を通してしまう
正常なフローを前提に設計されている場合でも、例外的な聞き方や手順を重ねることで、想定していない判断ルートに入ってしまうことがあります。
仕組み自体は正しくても、使われ方までは制御しきれていない状態です。
いずれも、設計書や仕様レビューの段階では、なかなか問題として浮かび上がってきません。
個々の部品は正しく動いていて、「明らかな欠陥」があるわけでもないからです。
ただ、AIペネトレーションテストを通じて、実際に触られたときの振る舞いを確認すると、はじめて「これはリスクとして整理すべきだ」と見えてきます。
生成AIに限らず、問題になりやすいのは、「想定外の使われ方をされたとき」の部分です。
AIペネトレーションテストは、その想定外を、事故が起きる前に一度だけ表に出すための作業だと感じています。
規制・ガバナンスの観点から見た重要性
AIに関するガイドラインや規制を見ていると、最近は共通して、ある一点が強く意識されていると感じます。
それが、「そのAIは安全か」ではなく、「安全性を確認する行為を、きちんと行っているか」という視点です。
完璧であることを求められているわけではありません。
むしろ、「どんな前提で使っていて」「どこまで確認したのか」、その過程を説明できるかどうかが重視され始めています。
診断の相談を受ける中でも、「何か事故が起きたらどうなるか」という話より、「何も起きていない今に、どこまで説明できる状態にしておくべきか」という話題が増えてきました。
生成AIは振る舞いが固定されていない分、「想定外は起きうる」という前提に立たざるを得ません。
だからこそ、事前にどう確認し、どう判断したのかが、そのまま責任の話になります。
今後は、AIペネトレーションテストを実施していないこと自体が、「なぜ確認しなかったのか」と問われる場面も、少しずつ増えていくのではないかと感じています。
それは怖さを煽る話ではなく、生成AIを業務で使い続けるための、一つの現実的な前提条件に近いものです。
まとめ:AIペネトレーションテストは「不安を煽るため」ではない
AIペネトレーションテストは、生成AIを疑うためのものでも、止めるためのものでもありません。
現場で向き合っていると、本当に必要なのは「危ないか安全か」を二択で決めることではなく、どこまでを任せ、どこからを人が引き取るのかを、一度きちんと整理することだと感じます。
- どこまで任せていいのか
- どこに人の判断を残すべきか
- どんな前提で、このAIを運用しているのか
AIペネトレーションテストは、その境界線を、落ち着いて引き直すための手段です。
何かが起きてから振り返ると、判断はどうしても後追いになり、選択肢も限られてしまいます。
一方で、何も起きていない今であれば、前提を並べ、優先順位を考え、無理のない形を選ぶ余裕があります。
生成AIは、これからも業務の中に入り続けます。
だからこそ、「信じて使う」前に、一度だけ立ち止まって確かめてみる。
その一手間が、結果的にAI活用の幅を狭めるのではなく、安心して使い続けられる選択肢を増やしてくれると、予防と診断の立場から、私は感じています。

投稿者プロフィール

- イシャン ニム
-
Offensive Security Engineer
15年以上の実績を持つ国際的なホワイトハッカーで、日本を拠点に活動しています。「レッドチーム」分野に精通し、脆弱性診断や模擬攻撃の設計を多数手がけてきました。現在はCyberCrewの主要メンバーとして、サイバー攻撃の対応やセキュリティ教育を通じ、企業の安全なIT環境構築を支援しています。
主な保有資格:
● Certified Red Team Specialist(CyberWarFare Labs / EC-Council)
● CEH Master(EC-Council)
● OffSec Penetration Tester(Offensive Security)
最新の投稿
 Soc2026.02.10オープンソースは、いまのセキュリティをどう支えているのか
Soc2026.02.10オープンソースは、いまのセキュリティをどう支えているのか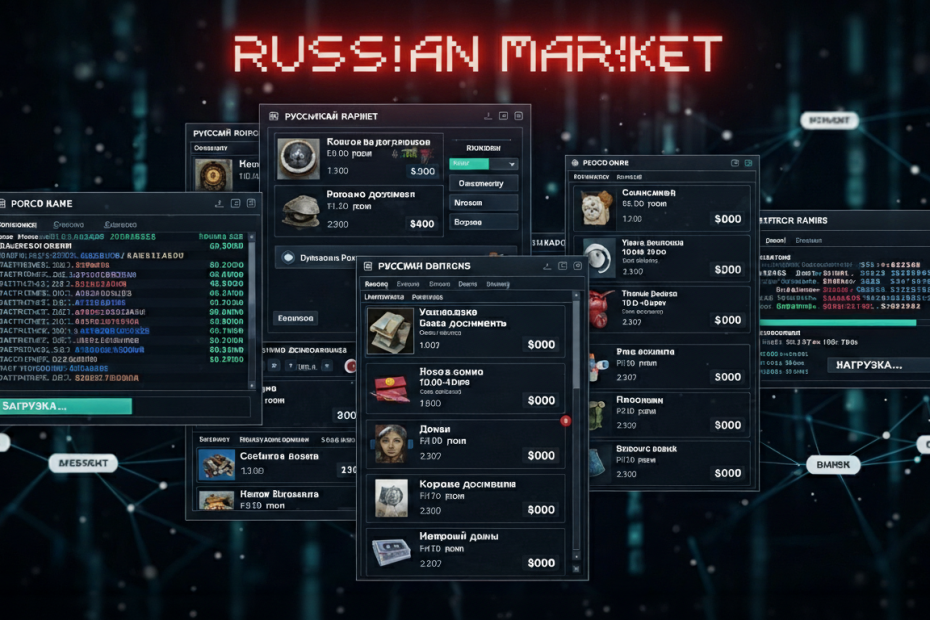 Black Hat2026.02.09Dark Web Market「Russian Market」が示す、いまの漏えいの形
Black Hat2026.02.09Dark Web Market「Russian Market」が示す、いまの漏えいの形 サイバーセキュリティの必需品2026.02.08パスワード管理が崩れたとき、最初に壊れるもの
サイバーセキュリティの必需品2026.02.08パスワード管理が崩れたとき、最初に壊れるもの LLM/生成AI2026.02.07AIセキュリティという新しい前提──信頼・リスク・耐性をどう築くか
LLM/生成AI2026.02.07AIセキュリティという新しい前提──信頼・リスク・耐性をどう築くか